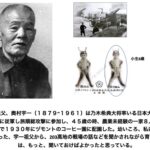【既報関連】5月19~22日にブラジリアで開催された「食の安全と飢餓との闘い、農業開発のための第2回ブラジル・アフリカ対話」では、食糧の安全性を確保し、飢餓を根絶すると共に、健康的な食べ物を家庭の食卓に載せるという、ブラジルとアフリカ諸国に共通する目標を実現するための話し合いや生産・備蓄の現場の訪問視察なども行われた。
アフリカと伯国は気候や植生が類似
特に目を引いたことの一つは、5月22日の閣僚会合で、カルロス・ファヴァロ農相が、50年前のブラジルは食糧輸入国だったが、異なる生態系に応じた技術の創出と普及により、農業部門の生産性、持続可能性、競争力が大きく向上したことや、アフリカ諸国の大半はブラジルと似た気候であること、ブラジルの牧草は全てアフリカの原産だから、牧草投資の遺伝的改良によって得た知識をアフリカに還元すれば、研究のために50年間も待つ必要がなくなることなどを挙げ、ブラジルで開発された技術をアフリカで再現する可能性などを強調したことだ。(1)
ワルデス・ゴエス地域統合開発相も、水の安全保障、家族農、魚の養殖、果樹栽培などの分野での経験と技術の交換は飢餓や貧困と闘うために不可欠と語った後、(気候や土壌が似ている)ブラジルでの経験や技術にはアフリカ諸国でも共用できるものが沢山あると強調した。(2)

見直されるセラード開発への日本の協力
このイベントの最中には、国家配給公社(Conab)の備蓄設備や、北東部から南東部の一部にかけて広がるセミアリド(半乾燥)と呼ばれる地域にある、ブラジル農牧調査研究公社(Embrapa)のウォータートレイル、ヌネス&シア果物生産ユニット、サンフランシスコ・パルナイバ渓谷開発公社(Cadevasf)の養殖部門の訪問・視察、Embrapa、Cadevasf、Nordeste銀行といった諸機関によるプレゼンテーションも行われた。
今回のイベントでの訪問・視察は北東伯(カアチンガ)が中心だが、農業関連の閣僚2人の発言などは、ブラジルで2番目に大きな生態系で、世界でも有数の生物の多様性を誇り、ブラジルの農業生産の中心的役割を果たしているセラードで、日本が協力して行った農業開発が、食糧輸入国から食糧輸出国への変貌に大きな役割を果たしたことを思い起こさせる。
「緑の革命」などとも呼ばれるセラードの農業開発における日本の協力は1970年代に始まり、現在も続いている。1973年のEmbrapaの設立と共に始まったブラジルと日本の協力プロジェクトは、大豆やトウモロコシの持続可能な供給確保に対する日本の関心から生まれた。24年8月4日付エザメ誌(3)は、Embrapaと国際協力機関(JICA)のパートナーシップは共通の利益を伴っていたという点で他のパートナーシップとは異なっていたという、エコノミスト兼研究者のジョゼ・エウスタキオ・リベイロ・ヴィエイラ・フィーリョ氏の言葉を紹介している。
それによると、当時の日本は米国からの大豆輸入に対する経済政策に直面しており、大豆を調達できる国を探していた。他方、ブラジルはセラードを穀物栽培に適した地域と考えていたという。

Embrapaの創設者の一人で約30年間総裁を務めたエリゼウ・アルヴェス氏によれば、Embrapa設立当時のセラードは茂みだらけで、過小評価され、重要とはみなされていなかった。同氏は、2023年に亡くなったアリソン・パオリネッリ元農相と共に、ブラジルの農業ビジネスの発展を牽引して来た。特に、セラードでの農業の変革に果たした役割は大きく、日本でも認められ、2024年7月に旭日章を授与された。
ゴイアス州、トカンチンス州、マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スル州、連邦直轄区、ミナス州西部、バイア州西部、マラニョン州南部、ピアウイ州西部とサンパウロ州の一部に広がり、ブラジルの国土の約25%を占めるセラードでの農業活動を促進するための技術・資金協力プログラムのプロデセルが設立されたのは1977年だ。

世界の食料安全保障にブラジルが貢献
アルヴェス氏がセラードを調査するために編成したチームの一員で、社会学者のジョゼ・パストレ氏は、アルヴェス氏は昼夜を問わず尽力し、プロジェクトを正しい軌道に乗せたとし、農業を主力とするブラジル経済の強さはアルヴェス氏に負うところが大きいと評価。Embrapa Soja(大豆部門)のアレッシャンドレ・ネポムセノ会長も、アルヴェス氏は戦略的で優れた科学的知識を持つ技術者で、ブラジルの農業ビジネスを、短期的にはもちろん、中・長期的な視点で考えており、セラード開発に非常に力を入れていたとしている。

日本の協力も得、科学的知識と大豆の直植えなどの革新的な農業慣行を融合させたプロジェクトは実を結び、茂みばかりだったセラードは世界最大の農業穀倉地帯の一つに変貌。しかも、直植えは事前の大規模で集中的な土壌準備を必要とせず、以前の作物の残渣や藁を敷くことで土壌被覆が維持され、土壌の保護や浸食の軽減、保水性の向上に役立ち、同地域の持続可能な開発とブラジルの農業部門の成功に重要な役割を果たしてきた。
セラードはブラジルの農業生産の60%、世界の大豆輸出の22%を占めており、マット・グロッソ州やマット・グロッソ・ド・スル州は世界経済フォーラムの報告でも大豆やトウモロコシの生産で知られている。(4)(5)
だが、ウクライナ紛争などが起きなくても、人口が増える中で生産性の向上が図られなければ、世界的な食料危機は起こり得る。アフリカ諸国との知識の交換や技術の移転がアフリカ諸国だけでなく、世界中を富ませ、世界規模の食糧保障につながる可能性がある。
(3)https://exame.com/agro/o-homem-que-reinventou-o-agro-no-cerrado-e-e-reconhecido-ate-pelo-japao/
(5)https://globe.asahi.com/article/12358808#:~:text=1970年代、ブラジル政府は,たのが、CPACだ。