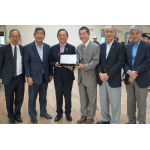「日本から陶芸をしにきたの?すごい!」
私が出会ったブラジル人の陶芸家はみな尊敬の眼差しでこう言ってくれる。
もちろん、悪い気はしない。でも、自分は大先生でも、売れっ子作家でもない。
「いやー日本で陶芸やっていたって言っても別に芸術大学とか出てないし大したことないよ」
と言ってみるものの、「いや、すごいよ君は!」と返される。
いやーそう言われるのちょっとプレッシャーやねんけど…とも思うが、ブラジル人陶芸家からいうと、日本で陶芸をしていただけでもすごいことなのだ。
というのも、ブラジルの陶芸界で活躍している方の中には、日本にルーツがある人たちがたくさんいて、日本で陶芸を学び、ここブラジルで素敵な作品を作っている。
また、サンパウロにはクーニャという陶芸でとても有名な街があり、そこは日本人や日本で陶芸を学んだ人たちが窯を築いたことがキッカケで陶芸が盛んになり、今や陶芸の街として知られるようになった。
そんなわけでブラジルでは、日本人陶芸家はとっても歓迎される環境にあると思う。
とはいえブラジルで陶芸に興味がある人がたくさんいるのかというと、そんなことはない。作家が手作りした作品を買って家で使うという人はとても少ないようにみえる。
日本みたいに料理によって器を選んだり、小さいお皿を組み合わせて器を楽しむ文化はないと言ってもいいだろう。
大皿にご飯、豆、お肉とサラダをどーんと盛って食べるのがブラジルのスタイル。
でも、ある日、ブラジルのレストランで、陶器の鍋で調理していることをアピールしているお店を見つけた。
ブラジルの代表的な料理であるフェイジョアーダや煮込み料理などが土鍋で調理されていて、”じっくりコトコト陶器の鍋で料理したほうが美味しい”、そういうイメージはブラジル人にもあることを知った。
土鍋で炊いたご飯を喜ぶ日本人と一緒じゃないか!
自然の中にある粘土を掘り、捏ね、成形して、炎や熱の力で焼く。
だから、陶器の鍋や器を使うとなんだか自然に近づいた感じがするのだと思うけど、これは人類共通の感覚なのかもしれない。それを知ることができてよかった。
さて、自分の活動に話を移そう。
サンパウロの東、イタケラの街にこどものそのという知的障がいのある方向けの入所施設がある。
こどものそのでは45年ほど入居者とともに陶芸作品を作り販売していて、私はその活動を手伝っている。
茶碗や湯呑み、小鉢など、ここがブラジルだということを忘れてしまいそうなぐらい、とっても日本的な作品を作っている。
同僚のブラジル人たちも、作品のことを”チャワン・ユノミ・コバチ”と呼んでいるので、そんな言葉が飛び交っている現場がちょっと面白い。

私の主な活動としては、作品の質を上げることと、入居者の方向けの陶芸ワークショップを行うことだ。
陶芸の作品は同じように作っても、微妙に一つ一つが違ってくる。
窯のどの位置に置くか、釉薬の厚み、窯を焚くときの温度、成形時の力加減。
そんなちょっとしたことの積み重ねで、作品はひとつひとつ違うものになる。
だから、おもしろくて、魅力があるのだと思う。
いろいろなものがボタンひとつで手に入る時代だからこそ、手で作った作品が我々には必要なのではないか。
そんなことをみんなに話しながら日々陶芸をしている。
陶芸やものづくりが好きな人が増えたら良いなと思いながら。