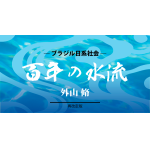そこで非常措置として、純ブラジル人に銀行を売却することにした。戦争が終わったら買い戻すつもりであった。
そこで非常措置として、純ブラジル人に銀行を売却することにした。戦争が終わったら買い戻すつもりであった。
売却後、経営者(宮坂国人、加藤好之)は身を退いた。
新しい経営者が乗り込んで来た。
以後、経営状態は急速に悪化した。預金引出しが続いただけでなく、融資金の回収も困難となった。
地方の支店長たち(日系)が、本店の方針に逆らう様にもなった。彼らは更迭され、後任にはブラジル人が任命された。
すると、これが不正を謀る…という具合で、難問は山積、銀行の信用は落ちる一方となった。
遂には内部の実情も把握できないほど乱れた。必死の資金繰りも追いつかず、半休業状態に陥った。
一九四二年末には、貸付金が預金を上回ってしまった。
ブラ拓に銀行部門を開設しようとした時、宮坂、加藤は予め(上部機関の海外移住組合連合会の)平生釟三郎理事長に、了解を求めた。その時、平生は、
「銀行は、移民社会に必要なものであるが…(略)…もし万一失敗するようなことがあると、社会に対し大変な損害を与えることになる。…(略)…全く銀行経営というものは、命がけの仕事である。皆にその覚悟があれば、やってもよろしい」(文中カッコ内は筆者注、以下同)
と、釘をさした。
その平生の忠告が、僅か数年で現実のものになってしまったのである。
なおブラ拓では、日本からの派遣職員は、一九四二年七月の交換船で帰国した。宮坂、加藤は乗船せず留った。立場上、当然のことだった。また南米銀行を放置することは、平生との約束上できなかった。
その頃の日々を、宮坂は晩年、筆者にこう語っている。
「今までに一番苦しかった時期」
加藤も、
「死ぬ思いをさせられた」
という言葉を文字にしている。
当時、二人は銀行に残った行員たちに繰り返し、こう言っていたという。
「終戦まで頑張ってくれ」
そう言われた一人に、橘富士雄という若手がいた。
北海道の出身で、小学校を卒業後、郵便局勤務を経て一九三二(昭7)年、二十歳の時に渡航、アリアンサ移住地に入植した。
彼はファゼンデイロつまり大農場主を夢見ていた。
が、翌年、腰掛けのつもりで、移住地内のブラ拓事務所に勤めていた時、サンパウロから出張してきた宮坂の目にとまった。そして巧く丸め込まれ、辞めることが出来なくなってしまう。
やがてカーザ・バンカリアができ、そちらに転任となり、サンパウロへ出てきた。そして前記の危機に巻き込まれた。
その危機の中、銀行は奇跡的に命脈だけは保っていた。
一九四三年、遠ざかっていた邦人の預金者が戻って来た。
この人々は預金をすることの危険は承知していた。が、
「日本民族独特の仁侠精神豊かな人々が多かった。それに支えられた」
と橘は記している。
そういう起死回生に近い状況下、次第に行員たちの中心的存在になって行ったのが橘で、後年、最高幹部になる。
海興、接収さる
次に、海興は開戦前に、すでに気息奄々という状態に陥っていた。
一九三四年の排日法以来、移民数が激減、それに伴い、東京本社が日本政府から受取る報奨金も同じことになったからだ。それも開戦でゼロとなった。
翌年、交換船が来ると、日本からの派遣社員は乗船した。支店長の宮腰千葉太は残った。海興はそれまでに十数万の移民を導入しており、これを放って支店長が帰国することなど、許されなかった。
この海興にも一九四三年四月、監査官が乗り込んできて、宮腰は「出社に及ばず」と追放される。(四、五章で登場した)幹部社員の坂本靖、長谷川武も同じだった。
以下、前章で利用した半田日誌を再び引用する。
「四月二十二日 香山さんから海興異変を聞く。宮腰さん、長谷川さん、それからもう一名が社を出されたとのこと…(略)…無論、退職金なしである。歯軋りするような思いだ。今に見ていやがれ!と思う」
海興ブラジル支店は、この後、接収されてしまう。
接収時の内情を記した関係者の手記があって、一邦人の絡んだ芳しからぬ噂が書かれていたが、行方不明になったまま…という話もある。