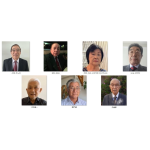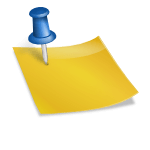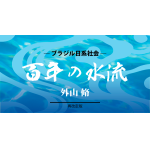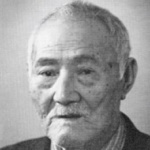一九五〇年、朝鮮戦争が始まると、パウリスタ新聞の東京支局の特派員となり、国連軍の従軍記者として現地に赴いた。
一九五〇年、朝鮮戦争が始まると、パウリスタ新聞の東京支局の特派員となり、国連軍の従軍記者として現地に赴いた。
どういうわけか、陸軍少佐待遇であったという。砲弾の音を聞きながら取材をした。
朝鮮から戻った後は、日本の皇族始め有名な政治家、芸能人をインタビュー、原稿を本社へ送った。
一方で「南桜会」仲間の帰伯に尽力、一九五三年、その最後の一人として自分も戻った。
アララクアラで事業を営みながら、サンパウロ新聞の通信員として、記事を寄稿した。
『蒼氓の92年』の著者、内山勝男は、そのサンパウロ新聞の編集長であった。
馬場は一九九八(平10)年、七十七歳で永眠した。かなりドラマチックな人生を送ったわけである。
故郷なき郷愁は、馬場がその生涯に書いた原稿を、一冊の本にまとめたものである。ただ、彼は出版前に故人となっており、友人たちが編集・出版作業を引き継いだ。
掲載記事によれば、馬場は戦後、南桜会仲間の消息調査をし、十数人が出征し七人が戦死したことを確認している。
そのことに関しては本のあちこちで触れているが、何故か、戦死者七人の詳細に関しては内山本が掲載している。
以下は、その要旨である。
一九二二(大11)年、リンスのバルボーザ植民地の甲斐茂は、勉学のため七歳で、単身、渡日した。両親の郷里熊本で農業を営む叔父の家へ身を寄せた。
二十歳で応召。連隊では優秀な成績で下士官適任証書が与えられた。
一九三九年、支那で戦死。二十四歳。これは支那事変中のことである。
両親宛ての手紙の中で「出陣に当たり国家の干城として捧げる死こそ誉れであり、戦死の知らせに涙を流して欲しくありません」としたためながらも「しかし、ただ一度だけ、皆さんと会ってからならば思い残すことはなかった、と思うと悲しくて泣けて来ます」と続けてあった。
同じく一九二二年。
ボンフィン・パウリスタ(サンパウロ州中央部)の鐘ヶ江久俊は、六歳で父久之助の福岡県の実家を継ぐため渡日した。
久之助は、実家の継承者であったが、米作で大きく成功していたため、永住を決め、代わりに息子を送ったのである。
久俊は一九四四年、ビルマの戦線で戦死した。二十九歳。
ここで一寸余談を挟むと、筆者は、この親子に関して、一つの記憶がある。半世紀以上も昔、二十代の頃のことである。サンパウロ新聞の記者をしていて、憩の園の何かの催しを取材に行った時のことであった。
取材の合間に、記者仲間で雑談をしていると、一人の老人が近寄って来て、自分の息子が日本へ行き戦死したという話をし始めた。
我々が、戦死した時の息子さんの年齢に近く、また日本から転住してきて数年で、日本の臭いを遺していたため、懐かしく思ったようだ
この老人が「自分は鐘ヶ江久之助」と名乗った。憩いの園を運営する救済会の役員ということだった。
筆者は、その名前は知っていた。成功者として知名度が高かったからだ。優しい話し方をする人だった。
会話中、単に「息子」とだけ言っていたが、僅か六歳で遠く日本へ旅立たせたのである。改めて、胸に迫るモノがあった。当時は船旅であった。甲斐茂も七歳だった。
一九三四(昭9)年。
イガラパーバ(サンパウロ州中北部)の藤尾千比古は十二歳で十歳の弟と渡日した。勉学のためで、両親の郷里である広島県の親戚に寄留した。
一九四三年、召集された。傷病兵として復員、浜松の陸軍病院に入院した。かなりの重傷であった様で、そこで死亡した。一九四四年末のことで二十二歳だった。
その遺品の中に、彼の上官だった川崎という分隊長が東京の自分の母親に宛てた手紙があった。それには「両親をブラジルに置いてきている部下の藤尾の境遇が不憫であるから、入院中の面倒をみてあげてほしい」と記してあった。
しかし、藤尾は迷惑をかけまいとしたのか、手紙は渡さずじまいだった。
一九三五(昭10)年、マットン(サンパウロ州中央部)の島袋貞雄は、九歳で勉学のため渡日、両親の故郷沖縄の親戚の家に寄留した。
一九四五年(昭20)、十九歳で学徒出陣、沖縄の激戦地で戦死。
一九三八(昭13)年、リンスの我那覇宗弘は家族と共に、渡日した。一九四五年、鹿児島七高に合格したが、入学を前に応召。両親の出身地である沖縄での勤務を志願、摩文仁で戦死。二十二歳。
彼には、宗成という兄がいた。宗成は、家族が日本に帰る時、気乗り薄で一人残った。が、父親の強い希望で、一九四一年、最後の日本向けの船で渡日した。出港間際、乗船を拒否して、関係者を手古摺らせたという。死を予感したのかもしれない。(つづく)