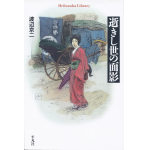日本独自の定型詩俳句や短歌は、今では世界に知れた最も短い詩であり、文学・哲学・芸術といえよう。俳句は、五・七・五の三句十七音で構成される。句の中に自然や季節のうつろいを表す「季語」を入れるというルールがあり、その季語によって詠う人の情感が奥行深く表現される。目に見えない心情を、具体的に言葉にして表現するのである。
現在は約70カ国以上に普及し、各国の言語で俳句がつくられているという。欧米では、ローマ字で「HAIKU」、中国では「漢俳(かんばい)」という名前で呼ばれ、親しまれているのである。
ブラジル日系社会の「ぶらじる俳壇」には俳句、短歌の秀作が居並び、日本語の美しさと奥深さ、美意識、自然に対する感受性を改めて学びつつ感慨深く拝読している。ブラジル俳句の先駆者は皇国殖民会社代理人として第1回の輸送を監督した上塚周平(俳号:瓢骨 1876~1935年)で、笠戸丸サントス着岸の際に詠んだ句が、「涸滝を見上げて着きぬ移民船」(上塚瓢骨)であり、ブラジル日系移民の俳句はここに始まると伝わる。瓢骨の命日は「瓢骨忌」という季語にもなっていると紹介されている。(https://www.ndl.go.jp/brasil/column/haiku.html)
人生の重荷を下ろし、心軽やかに老境を過ごしたい
超高齢社会の現代、100歳でも心身ともに充実した人生を送っている高齢者もいる。その一方、多くの場合は、病気、親子関係、金銭問題、終の始末といった不都合な問題を抱えている。これは現代社会の老人の問題かというと、そうではない。すでに古代から人間に付き纏う高齢期の悩みであった。
それでは、どうしたら「過去を手放し、心軽やかに老境を過せるか」
◎過去の出来事を後悔や足かせにするのではなく、あの失敗があったればこそが、今の自分があるのだ。自信を持って老齢の自分を認めよう。
◎やり残したことに、今だからこそ取り組める、と限りある老後に本当の自分らしい生き甲斐作りを見出す。
この願望を充たせる答えがあるだろうか。ヒントを探して『おくのほそ道』を再読した。
俳聖・芭蕉に習う老いの生き方

芭蕉は旅を好み、紀行文を幾つか残している。その中でも、芭蕉の『おくのほそ道』を知らない人はいないであろう。この本は、単に紀行本というより、老齢の芭蕉が構築した「不易流行」と「かろみ」を含んだ人生訓が詠われている。
芭蕉は旅立つ前に、素朴な庵を離れる。その時に詠ったのが次の歌である。
草の戸も 住み代わる世ぞ 雛の家
(戸口が草で覆われたこのみすぼらしい深川の宿も、私にかわって新しい住人が住み、綺麗な雛人形が飾られるようなはなやかな家になるのだろう)
全編を読み返すほどに美しい日本語と深い感慨のこもった「五・七・五」3句17音で構成された名句の数々は、深く心に残って離れないのである。
『おくのほそ道』は次のように始まる。
《月日は百代の過客にして、行交う年も又旅人也。
舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老いをむかうる物は、日々旅にして旅を栖みかとす》
(現代語訳)月日は百代にわたって旅を続けて行くものであり、来ては去り去っては来る年々も、また同じように旅人である。舟の上に身を浮かべて一生を送り、旅人や荷物を乗せる馬をひいて生涯を過ごし、老年を迎える者は、日々が旅であって、旅そのものを常のすみかとしている。
「奥の細道」に描かれた陸奥(みちのく)への旅は、万葉時代の歌人たちが創った想像上から続く枕詞(まくらことば)の宝庫を自分の目で確かめ、「老いの道」を沈思黙考するための旅であった。
「時は永遠の旅である。人生は旅である。人は皆、旅の途中で一生を終えるのである。西行、能因など、昔も旅の途上で亡くなった人は多い。私もいくつの頃だったか、吹き流れていくちぎれ雲に誘われ漂泊の旅への思いを止めることができず旅に出ることを決意した」
芭蕉は西行500回忌に当たる元禄2年(1689年)の3月27日、弟子の曾良を伴い下野・陸奥・出羽・越後・加賀・越前など、未知の国々を巡る旅は、全行程2400キロ、150日間の旅であった。
俳聖芭蕉の人生
松尾芭蕉(まつお・ばしょう1644年―1694年)。生まれは伊賀国阿拝郡(現在の三重県伊賀市)で、土豪一族出身の松尾与左衛門の次男として生まれた。松尾家は平氏の末流を名乗る一族で、当時は苗字・帯刀こそ許されていたが身分は武士ではなく農民だった。兄弟は、兄と姉一人、妹三人がいた。幼名は金作。通称は甚七郎、甚四郎。名は忠右衛門、のち宗房。俳号としては初め宗房を称し、次いで桃青、芭蕉と改めた。
明暦2年(1656年)、13歳の時に父が死去し、兄が家督を継いだ。若くして伊賀国上野の侍大将の嗣子・主計良忠(俳号は蝉吟)に仕え、その厨房役か料理人を務めていたようであるが、主君・良忠とともに、京都にいた北村季吟に師事して俳諧の道に入った。
ところが良忠が25歳で歿し、その後、宗房は江戸へ向かった。そして日本橋小田原町に住み始め、そこで江戸俳壇の俳人たちと交流を持ち、初めて号「桃青」を用いた。桃青は宗匠となって文机を持った。ところが庵が火災で全焼し、母まで亡くす。この出来事は芭蕉に強い無常観を抱かせることになった。
日常生活では(1677年)、水戸藩邸の防火用水に神田川を分水する工事に携わった事が知られる。仕事は、労働や技術者などではなく、人足の帳簿づけのような仕事だった。これは、経済的に貧窮していた事や、当局から無職だと眼をつけられる事を嫌ったものと考えられる。当時の俳壇は、弟子の数や収入の多さを競う風潮があった。芭蕉はそのような生活を嫌った。弟子たちの支援を得て職業的な俳諧師となって、隅田川対岸、深川の質素な庵で隠遁生活を始める。このころに芭蕉と改名する。
しかし再び、天和2年(1682年)12月28日、天和の大火(いわゆる八百屋お七の火事)で庵を焼失し、翌年の冬には芭蕉庵は再建された。この出来事は芭蕉に棲家を持つ事の儚さを知らしめたのであった。
いずれにしろ彼は安定した俳句の師匠の生活を捨て、俳諧の純粋性を求め、世間に背を向けて老荘思想のように天(自然)に倣う中で安らぎを得る方向に変更していった。
旅立ちの歌
行春や 鳥啼 魚の目は泪
(旅立ちの別れをまるで自然界も泣いているようではないか。過ぎ去る春に、鳥も泣き、魚の目も最後の別れを惜しむように涙で潤んでいるようだ)
それでは、名句が詠われた場所をいくつか挙げながら芭蕉の旅の心情を辿ってみる。(名句はすべて現代語訳)
日光の宿主、仏五左衛門
三月三十日、日光山のふもとに泊まる。宿の主人の名は仏五左衛門。いったいどんな種類の仏がこの穢れた世に姿を現して、私のような乞食巡礼の旅のみすぼらしい者をお助けになるのだろうかと、主人のやることに心をとめて観察していた。
すると、主人は知恵や分別にすぐれているのではなく、ただひたすら正直一途な者なのだ。論語にある「剛毅朴訥(ごうき・ぼくとつ)」という言葉を体現しているような人物だ。つまり、意志が強く、正直で飾り気がない。こういう者こそ尊ばれなければならない、と芭蕉は思った。
日光にて
四月一日、日光の御山に参詣する。昔この御山を「二荒山(ふたらさん)」と書いたが、空海大師が開基した時、「日光」と改められた。
大師は千年先の未来までも見通すことできたのだろうか、今この日光東照宮に祭られている徳川家康公の威光が広く天下に輝き、国のすみずみまであふれんばかりの豊かな恩恵が行き届き、士農工商すべて安心して、穏やかに住むことができる。
あらたふと青葉若葉の日の光
(意味)ああなんと尊いことだろう、「日光」という名の通り、青葉若葉に日の光が照り映えているよ。
白河の関

最初は旅といっても実感がわかない日々が続いたが、白河の関にかかる頃になってようやく旅の途上にあるという実感が湧いてきた。…
卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良
(意味)かつてこの白河の関を通る時、陸奥守竹田大夫国行(むつのかみたけだのだいふくにゆき)は能因法師の歌に敬意を表して衣装を着替えたという弟子・曾良の歌。私たちはそこまではできないがせめて卯の花を頭上にかざして、敬意をあらわそう、ということだ。
松島
古くから言われていて今さら言うことでもないのだが、松島は日本一景色のよい所だと芭蕉は述べたが歌は詠んでいない。「松島や ああ松島や 松島や」は、松尾芭蕉が詠んだ句ではなく、他者が創作した句であると言う。芭蕉は風景に圧倒されて歌を詠めなかった。
平泉
藤原清衡・基衡・秀衡と続いた奥州藤原氏三代の栄光も、邯鄲一炊の夢の故事のようにはかなく消え…中略…国は滅びて跡形もなくなり、山河だけが昔のままの姿で流れている、繁栄していた都の名残もなく、春の草が青々と繁っている。笠を脱ぎ地面に敷いて、時の過ぎるのを忘れて涙を落とした。
夏草や 兵どもが 夢の跡
(意味)奥州藤原氏や義経主従の功名も、今は一炊の夢と消え、夏草が茫々と繁っている。
芭蕉はかねてその評判を聞いていたので、中尊寺金色堂と経堂(1951年国宝第一号)の扉を開く。経堂には藤原三代頭首の像、光堂にはその棺と、阿弥陀三尊像が安置してある。なお、マルコ・ポーロの「東方見聞録」の黄金の国ジパングは中尊寺金色堂を指しているのではないか、という説がある。
しかし、その奥州藤原氏の所有していた宝物の数々は散りうせ、玉を散りばめた扉は風に吹きさらされボロボロに破れ、黄金の柱は霜や雪にさらされ朽ち果ててしまった、と芭蕉は嘆息している。
五月雨の 降りのこしてや 光堂
(意味)全てを洗い流してしまう五月雨も、光堂だけはその気高さに遠慮して濡らさず残しているようだ。
立石寺
山形藩の領内に、立石寺という山寺がある。特別景色がよく静かな場所だ、一度は見ておくべきだと、人々が勧めるので、尾花沢から引き返した。
景色は美しく、ひっそり静まりかえっている。心がどこまでも澄み渡った。
閑さや岩にしみ入る蝉の声
(意味)ああ何という静けさだ。その中で岩に染み通っていくような蝉の声が、いよいよ静けさを強めている。
この歌は、内面の静けさと、蝉の声という躍動感を対比させ、芭蕉の悟りの道に至る歌という。
最上川を詠う
五月雨をあつめて早し最上川
暑き日を海にいれたり最上川
北陸道に至って、新潟の荒く波立った海の向こうに佐渡島が見える。そして生まれた名句が、
荒海や佐渡によこたふ天河
芭蕉は8月下旬に大垣に着き、約5カ月の旅を終えた。
旅に病んで夢は枯野をかけ廻る
この句が事実上最後の俳諧となる。1694年(元禄7年)10月12日、現在の大阪市中央区久太郎町3丁目で、51歳で逝去。14日葬儀、遺言に従って木曾義仲の墓の隣に葬られた。焼香に駆けつけた門人は80名、300余名が会葬に来たという。

不易流行と「かる(軽い)」の境地とは
この旅で、芭蕉は歌枕の地に実際に触れ、変わらない本質と流れ行く変化の両面を実感した。いつまでも変わらない本質的なもの(不易)と、時代の変化とともに変化していくもの(流行)の両方を大切にする俳句の考え方の基礎を築いた。
芭蕉にとっての「軽み」とは、「高く悟りて俗に帰す」。すなわち、自然を鑑賞する中で最も豊かなもの、最も心に残る時をあえてさらりと言い表すこと。「松のことは松に聞け」と言うことである。
芭蕉の50年の生涯は、ある時期は立身出世のコースを想定しながら一生懸命生きたこともあった。またある時は、人生に挫折して、出家を考えた。
このように、誰にとっても人生は艱難辛苦の旅である。苦しみぬいた挙句、ストンと肝に落ちることがある。その時が執着が抜けるときと思うと、どれほど気分が軽くなるであろうか。そこに至れば、晴れやかな気持ちで一句ひねり始めているかもしれない。
【参考文献】
◎青空文庫「おくのほそ道」松尾芭蕉 杉浦正一郎校註
◎山本健一「奥の細道 現代語訳・鑑賞(軽装版) 」出版社 飯塚書店