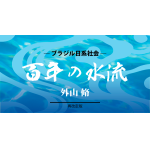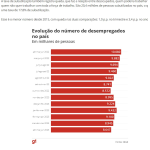そして東山。
ここは総支配人の君塚慎が、一九四〇年に帰国、山本喜誉司が後を継いでいた。
開戦後、山本は本社からの派遣社員は交換船に乗せ、自身は見送った。家族もそれに従った。
当時、東山は農場(含、酒造所)、商社、小銀行、絹織物工場、絹製品の小売店、鉄工所を経営していた。
農場=東山農場=はその開設後、カンピーナスのほかピンダモニャンガーバにも広大な土地を取得していた。が、後者は売却した。外資のため軍部に接収されるかもしれない、という情報が入ったことによる。
一九四二年、カンピーナスの農場に監査官が乗り込んできた。
ここも接収される危惧が生じた。
山本は、それまでに交友関係を築いていたブラジル人有力者の協力を得て、回避しようとした。
その時、彼らの勧めで、自分が長年続けて来たカフェーの害虫対策に関する研究資料を、ポルトガル語で発表した。
「我々は単に営利を目的とするだけでなく、業界のために、こういうこともやって、この国に貢献しています」という宣伝が目的であった。
他にも手を打ち、接収は免れた。
商社=カーザ東山=は、カフェーや綿の委託販売業者として、邦人農業界と深く関わっていたが、自ら休業した。日本への輸出が総てだったからである。
小銀行=カーザ・バンカリア東山=は、監査下に置かれ、預金者の生活費引出しに応じる部門以外は、休業に近い状態となった。
絹織物工場、絹製品の小売店、鉄工場は自主的に閉鎖した。やはり開戦の影響が大きかったからである。
御三家は、以上の如くであったが、いずれも最高幹部たちが、日本外務省の役人とは違って、交換船に乗らなかった事実は、後世、無形の勲章となった。
しかし当時は、存亡の淵に立たされており、御三家の名に相応しい「日系社会の拠り所」になることはできなかった。
これは多くの人々を失望させた。
他の企業の場合
御三家以外では、日本からの進出企業がサンパウロ、リオ、パラナ三州そしてアマゾン地方に十数社あった。内、数が多かったのが商社で、日伯綿花、三井物産、東洋綿花(南米綿花)、兼松、伊藤忠、ほか中小の数社であった。(カッコ内は現地法人名)
この商社は五章で記した様に、一九三五年の平生使節団の訪伯を機に進出、綿の対日輸出を行っていた。ために全社が閉鎖した。
その原綿の精製を行うため設立されたブラスコット(日伯綿花の現地子会社)は存続できた。
精綿が日本以外に輸出されることになったからである。前記の様に輸出は政府が奨励していた。
進出企業は、商社以外では、拓殖事業に関わっていたところが幾社か在った。
内、モジの片倉農場は、輸出用の紅茶の生産が主業務であったため、事業を継続できた。
サンパウロ州西部アヴァニャンダーヴァの(関西財界の川西清兵衛らが設立した日伯拓殖会社の)バーラ・マンサ農場は「進出時、適切な登記がされていなかった」という理由で接収され、競売に付されてしまった。
パラナ州北部バンデイランテスの野村農場は、日本の開戦時に、ブラジル人の知人に農場を貸与するという便法をとった。日系の従業員は、そのまま就労を続けた。
ただ支配人の牛草茂まで、そうしたら目立ち過ぎるというので、農場外に移った。
ところが、その貸与した相手が日本軍の旗色が良い間は、最初の契約を忠実に実行したが「旗色が悪くなると、農場の資産を徐々に自分の名義に切り替え始めた」と牛草側は戦後主張、係争となり、それは長く続いた。
バンデイランテスの西四十数㌔、現ウライの(山科礼蔵東京商業会議所会頭らの出資による)南米土地会社の大型入植地は、一九四一年時点で、ロッテ=区画=購入者は計五〇九人、内日系人は二二一人となっていた。
ここは一九四四年に監査下に置かれた。
一九四六年、戦後になっても、それは終わらず、監査官をしていた一ブラジル人が、日系の支配人を解任した。さらに会社の土地を不正売却した。
それを、ここでラミー関係の事業を起こそうとしていた藤平正義というやり手の男が見破り、告発、追放した。(この藤平は次章以降で再登場する)(つづく)