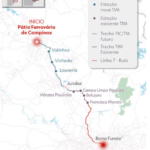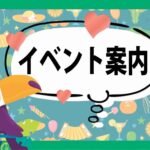教育界での長年の功績と、ブラジルと日本の架け橋としての歩みに敬意を表し、ある特別な祝賀会が開催されました。サンパウロ州教職員センター(Centro do Professorado Paulista)での教員の労働時間短縮キャンペーンも、この日はひととき足を止め、その主役を称えるために時間を捧げたのです。
祝われたのは、同センターの会長を務めるロレターナ・パオリエリ・パンセラ先生の99歳の誕生日。彼女の名を冠した合唱団による歌声が、会場に温かく響き渡りました。
ロレターナ先生はピラシカーバ市出身。イタリア移民の家庭に生まれ、人生のすべてを教育に捧げてきました。生まれたのは1920年代、当時のブラジルでは成人の約8割が読み書きできなかった時代です。
彼女は生徒として、そしてやがて教師として、ブラジル教育史の重要な転換期を幾度も見届けてきました。たとえば「新教育運動」や職業訓練校の拡充、1930年の教育・保健省創設、1961年の教育基本法(LDB)の成立などが挙げられます。
1930年代、日本の移民社会にとっては試練の時代でもありました。ブラジルでは当時、強い国家主義の流れのなかで、およそ400校もの日本人学校が閉鎖されました。教育相だったフランシスコ・カンポスは国家統制の象徴ともいえる1937年の「エスタード・ノーヴォ憲法」も起草し、外国人への政治的弾圧が強まる中、日本移民の子弟教育は困難を極めました。
そんな中、ロレターナ先生は日系移民家庭の教育的苦境に心を寄せ、多くの日系人の子どもたちに授業を行いました。その関わりはやがて大きな信頼と絆となり、1993年には「ブラジル日本教育連合会(UEBRAJA)」を設立。以降、サンパウロやクリチバ、そして日本でも「日伯教育シンポジウム」を通算17回にわたり開催し、日伯の教育交流に尽力しました。
とりわけ2008年、サンパウロで行われた第17回シンポジウムでは、州教育局と協力して「ビバ・ジャポン」プログラムが導入され、ブラジルの学校で日本文化への理解とリサーチ活動が展開されました。同年には、移民船「笠戸丸」の名を冠した「カサトマル勲章」が彼女に贈られ、日伯関係への貢献が公式に讃えられました。
なお、彼女の名を冠した「ロレターナ・パオリエリ・パンセラ合唱団」には、日系二世の元教員たちも参加しており、かつて教壇で響かせていた声を今は歌声として届けています。
2019年、ロレターナ先生は私にこんな話をしてくれました。「日系の女性が自然と教育者になっていったのは、移民家庭にとって教育が最優先だったから。教室は神聖な場だったのです」。移民という経験が育んだ勤勉さ、規律、学問への尊敬、そして集団への配慮といった価値観は、今も第四世代の若者たちに受け継がれ、教育の現場で息づいています。
1945年から1986年まで、実に41年にわたり教職に就いたロレターナ先生。教育の質と教員の地位向上を一貫して追求し続けました。現在も教職員センターの名誉ある会長として組織を支えながら、若きリーダーたち――たとえば、労働時間短縮運動を推進するアレッサンドロ・ソアレス教授らの活動を力強く後押ししています。その存在は、より公正で学びある社会の礎を築き続けているのです。
2023年、ポッドキャストに出演したロレターナ先生は、自らの人生をこう総括しました。詩人フェルナンド・ペソアの言葉を借りて――「Tudo vale a pena se a alma não é pequena(心が広く、大きな志を持っていれば、どんな困難にも意味がある)」。
その魂の大きさこそが、日伯友好130年の節目にふさわしい象徴なのかもしれません。