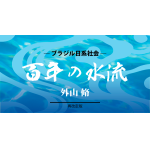重信は一九二四(大13)年、愛媛県に生まれた。一九三八(昭13)年、十四歳の時、家族と共にブラジルに渡った。
重信は一九二四(大13)年、愛媛県に生まれた。一九三八(昭13)年、十四歳の時、家族と共にブラジルに渡った。
一九四二年、家族がクリチーバで食糧品店を営んでいた時、父親が重信の戸籍を作り変え、ブラジル人にした。悪く言えば戸籍の改竄であるが、当時は、そういう融通が利いた。
その時、年齢も実際より二歳上にした。十八歳だったが二十歳とした。
父親は幾つかの理由で、そうした方が都合が良いと判断したのであるが、これが裏目に出た。
同年、重信はブラジル国籍で二十歳であったため召集され、二年後にイタリア戦線へ送られた。
それ以前、母親が軍隊からの脱走を勧めたことがある。当時、脱走は珍しくなかった。が、当人は「日本人の体面に泥を塗ることになる」と断った。
そして激戦地モンテ・カステロで戦死した。その時、負傷者を担架に乗せて運んでいた。雨の中を日本語で「バンザイ、バンザイ」と叫びながら駆けていた。
彼が倒れた後、雨が止み太陽が現れた。それが日章旗の日の丸の様であったという。
それから六十数年後の二〇〇九年、筆者は出征した日系兵士の中に生存者は居ないか、と探してみた。皆、相当の高齢になっている筈であり、難しいかもしれない、と思ったが…。
しかし協力者、ブラジル陸軍の京野ヨシオ退役大佐のおかげで、一人見つかった。児玉ハウーという名前であった。サンパウロ市内にある在郷軍人会の本部で会うことになった。
その本部に行くと、老齢の人々が懐かしげに歓談していた。イタリア戦線への出征兵士の戦友会ということだった。
筆者が腰かけた席の斜め向かい側に、戦場での思い出を、唾を飛ばしながら、夢中で喋っている非日系の老人がいた。余程懐かしそうな様子であった。
周囲を見回してみたが、日系らしい顔つきの人がいない。
京野大佐が「こちらが児玉さん」と、近くに居た人を引き合わせてくれた。
が、ブラジル人である。よく見ると目つきは日系だった。日本語は全く話せない、という。隣に日系の夫人もいたが、やはり同じだった。二人は表情の作り方も仕草も、完全にブラジル人のそれであった。
ハウー老は九十二歳だという。至極、元気そうだった。開口一番、微笑しながら、
「私の両親は笠戸丸移民だ」
と誇らしげに言った。
一九一七年に生まれ、少年時代はプレジデンテ・プルデンテで過ごした。
長じて、サンパウロに出て農機具商で働いた。
一九四四年に召集された。その数年前に陸軍の短期研修コースの訓練を受けたことがあり、その関係だろう、という。
一兵士としてイタリア戦線に送られた。ドイツ軍と交戦中の最前線で、後方の補給基地との間を往復する貨物自動車の運転手をした。死傷した兵士を後方へ、兵糧弾薬を最前線へ運んだ。
一九四五年二月、モンテ・カステロでドイツ軍の砲撃を受け、足に重傷を負った。近くに居た少尉の首が身体から千切れて吹っ飛ぶのを見た。
その後、米国に送られて治療を受けた。翌年、退役した。
筆者は、
「日本の同盟国ドイツと戦うことに、何か感じなかったか?」
と聞いてみたが、答えは、
「向こうは向こう、コッチはコッチ」
と、カラリとしたものであった。
「ブラジル軍の指揮官の中には、ドイツ人もいた。それがドイツ軍と戦っていた」
とも付け加えた。
最後に「イタリア戦線へ出征した日系兵士が、もう一人生きているかもしれない」と教えてくれた。モジの何処かに住んでいる筈だという。
筆者は早速、モジの知人たちに問い合わせてみた。が、誰も知らない。モジといっても広く日系住民は多い。
半ば諦めかけて数カ月後、別の目的の取材先で偶然手がかりを得、自宅を訪れて話を聞いた。二〇一〇年のことである。
その人は身体が衰弱しており、聴力も弱っていた。聴力のことは予め聞いていたので、ポルトガル語で書いた質問書を用意して行った。が、視力も衰えており読めない。
こちらの質問を、家人が当人の耳元で、何回も繰り返した。すると、やっと話し始めた。日本語だった。
「年齢は八十八歳、両親は沖縄県人。自分の名前はナカソネ・サツキ、日本文字でどう書くかは知らない。昔のことは殆ど忘れた」という。(つづく)