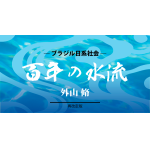なお、吉川の拘置が長引いていた間、興道社は名称を変更している。その理由に関しては、明確ではない。
改称の時期は、一九四五年、終戦直前である。月日に関しては複数の説がある。
その新しい名称が臣道連盟であった。(当時の使用文字は臣道聯盟)理事長には、拘置中の吉川が指名された。
臣道連盟という名称は、字画といい語感といい格調高く、団体名としては悪くない。が、独創ではない。「臣道」は日本で昭和十五年、一九四〇年から流行した言葉である。
近衛文麿首相によって「臣道実践運動」が提唱され、政界初め広く国民の支持を集めた。以後、国策の基本となり、臣道という言葉は盛んに使用された。
臣道連盟は、その綱領や吉川が記した文書によれば、大東亜共栄圏の建設を翼賛するため、共栄圏へ移動することを目的とし、その準備のため、青年層を対象とする日本精神、日本語の教育に着手していた。
大東亜共栄圏については、八章で記した。
臣道連盟のその後については次章以降に譲る。
二種類の出征(上)
この辺で、この大戦中の若者たちの出征に触れておく。
日系社会からは、少数であったが、二種類の出征兵士が出ている。
「開戦前に日本へ帰国、日本兵として戦場へ行った者」
と、
「ブラジル軍の兵士となり、イタリア戦線へ送られた者」
である。
まず日本兵として戦場に行った者たちから記す。
笠戸丸移民以来、邦人の中には少比率ながら日本へ帰国する人々がいた。家族揃って…ということもあったが、その一部あるいは一人で…ということもあった。
この内、ブラジル生まれに関しては、帰国という言葉は、不適切かもしれない。以下、渡日という言葉を使う。
帰国の動機は錦衣帰郷その他色々だった。渡日のそれも幾つかあったが、少年期の子供が勉学のため…という様なこともあった。
帰国・渡日は一時的でブラジルに戻った場合もあれば、戻らなかった場合もある。
一九三〇年代に、完全な帰国・渡日が増えた。これは、五章と七章で記した排日法の成立、日本語学校の閉鎖で、この国に嫌気がさして…という動機が多かった。
彼らの中の青少年の場合、日本で兵役適齢期になった者が相当数いた。
日本生まれは勿論、ブラジル生まれの場合も日本国籍を取得していたから、徴兵検査を受け召集されれば兵士となった。志願した者も居た。
その内、どれ位の人数が出征、戦死したかは把握されていない。調査されたこともない。
終戦から半世紀以上経って、漸くそれに僅かに触れた資料が現れた。馬場謙介著『故郷(ふるさと)なき郷愁』と内山勝男著『蒼氓の92年』である。
その話に入る前に、馬場のことを少し紹介しておく。馬場は一九二一(大10)年、サンパウロ州中央部アララクアラのモツーカで生まれた。
そこは、当時は開発地であり、三章で触れた東京植民地があった。その創立者馬場直が彼の父親であった。
東京植民地は、風土病で大量の犠牲者を出した。が、それにも屈せず、苦心惨憺、植民地を維持した。
その上、学校を建設、ポルトガル語と日本語の両面での教育に力を入れ、模範校として知られた。
謙介は、そこで学んだ。優秀な成績を上げたのであろう…一九四一年、日本の文部省の招聘で留学生として渡日した。前章で登場した平田進と同期だったことになる。
東京第三師範学校に入学した。
戦時中は平田らと、同じブラジル生まれの仲間に呼びかけ、互いに連絡を密にして戦争を乗り切ろうと「南桜会」という集まりを作った。
会長が平田で、会員との連絡役を馬場が務めた。
当時、その仲間は全国で五十余人、うち半数が京浜地区に住んでいた。
馬場は師範学校の本科を一九四三年に終了、翌年、東山の日本本社に入社した。同社は東南アジア各地でも諸事業を行っていた。シンガポールで働き始め、スマトラで終戦を迎えた。
一九四六年、日本へ引き揚げ九州各地を、ルンペン生活をしながら放浪した。雑のうを肩に農家の門口に立ち「仕事はないか?」と訊ね歩いた。何軒か歩けば、飯を施してくれたり仕事をくれたりする処もあった。夜は駅のベンチで寝た。
その後、上京、GHQ(八章参照)に勤務した。(つづく)