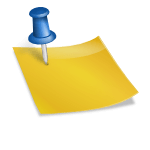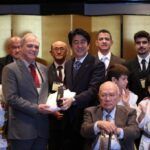近くに、別の安旅館を見つけた。
少し離れた所でリュックを外し、見えないように隠し置いた。
そして、神妙な顔付きをして旅館に入った。
「わたくしは、一人で旅をする者でございます。一晩だけでも泊めていただけるでございましょうか?」
「ハイ、ハイ、どうぞ!」
「それでは、荷物を取りに行って参ります」
「お車でいらしたのですか?」
「いえ、駅より歩いてまいりました」
「・・・・・」
翌朝、広島駅構内のポスターで近くに日本三景の宮島がある事を知った。
リュックを駅のロッカーに預け、午前中見学する事にした。
始めて訪れた宮島の厳島神社は日本人の信仰と美意識を集約して表現するように思えた。
私は、ギリシャのアテネでアクロポリスの神殿跡を訪れたが、天に向かってそそり立つその規模の壮大さに人間を【超越した存在】への人間の信仰の【強さ】や【深さ】を感じなかった。
反対に自然に拮抗する、人間の強烈な自己主張を感じた。
しかし、厳島神社では、人間の建造物がその存在を誇らせずに【あるがままの自然】と調和共存し【自然への帰依】があった。
この【自然への帰依】という印象は、その後訪れたインカ帝国のマチュピチュ遺跡でもその規模は大きさにかかわらず感じた。
午後、鉄道で広島から宇都宮まで北上し一泊した。
翌日の夜明け前に出立し、盛岡、野辺地、下北、丈畑と乗り継ぎ、下北半島、恐山麓の薬研温泉を目指した。
北緯40度近くの盛岡あたりから車窓より見える日本の自然は、その美しさを増していった。
濃緑の樹海に覆われたなだらかな岩手山を見ながら啄木の詩「ふるさとの山は有難きかな」「ふるさとの山に向かいて何も言う事なし」を思い出した。
20才にして、己の生まれ出ずる国を去り、60才近くの今初めて己れの生れ出でた国へ帰ってきた。
私の胸中は、《ふるさとの山は有難きかな》《ふるさとの山に向かいてなにもいうことなし》の言葉にただただ尽きた。
思えば、ボードレールの「悪の華」に心酔していた20才前の私には、啄木の詩などあまりに単純幼稚で到底詩などとは思えなかった。だが、啄木の詩を幼稚と感じたのは実は私自身の心と精神が幼稚であったからで、その詩はあたかも人間の息吹の如く【自然そのもの】であることを今となって痛感する。
薬研温泉では、2食付き8千円の宿を見つけた。
翌朝、ヒバの国有林のある湯川渓谷にそって薬研まで散策した。
人気のないひっそりとした河原の共同露天風呂で、紅葉を眺めながら朝湯を浴びた。
私は、とても幸福な気持ちになった。
朝湯後、本州最北端の大間を目指し、大畑から乗り合いバスに乗った。
バスは、太平洋の波打ち際を走った。
浜辺に人影はなく海鳥が群れをなしていた。
この辺りは、去年旅をしたアルゼンチン、パタゴニアのヴァルデス半島と同緯度にあるが、半砂漠化した乾燥ステップ地帯のヴァルデス半島とは、対照的に下北半島は雨に恵まれ、緑が濃かった。
大間に着くと急に天候が変わり、強風雨が襲来した。
函館港フェリー船は、予定通り出港したが、津軽海峡を眺めながらの船旅を楽しみにしていた私は、がっかりした。
あるカナダ人が旅行雑誌の随筆で、「大間は本州最北端と言って自慢するけれど、それでもカナダの最南端のそのまた南にあるとからかい、カナダ人やヨーロッパ人から見たら、日本は南国であると指摘していたが、私も全く同感だった。
そもそも、東京の緯度はアフリカのアルジェリアやチェニスと同じであり、北海道の最北端でさえ、南ヨーロッパ、アドリア海のヴェニスと同緯度にある。(つづく)