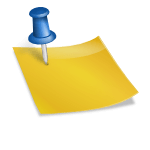第11話―躾
家の前の軒下、歩道、延いては道端まで毎日水をまいて掃除するのは、私たち日本人には幼い時から記憶に刻まれた光景であり、日本の情緒ある光景でもある。それが子に孫にと引き継がれた日本の「躾と美」の習慣である。
ところがここブラジルでは、それが全くない。家の中は我々日本人にはまねが出来ないぐらいキチンと綺麗にするのだが、家の外、特に公共の場となるとまったくおかまいなし。それどころか逆にゴミをポンポンとほうり出して汚くしてしまう。だれかが掃除するだろう、掃除するのは市の清掃局の仕事と完全に割り切っている。
住宅街にある私の家の前も車がゆうゆうと行き交えるほどの幅のある道であるが、とてもおもしろいことがある。
この道のちょうど私の家と向かいの家の前の両側に排水溝がある。向かいの家は3年程前に改築手直しをしてきれいにし、歩道のところまでタイルを貼ってきれいにしたまでは良いが、その家の庭に大きな木があり、毎日のように木の葉が舞い降り、それが雨で排水溝の網に引っ掛かり、雨水が通りにくくなり、道が水浸しになる。
それが何回も続くと水はどす黒くなってとても汚くなり、車が通るとその水がその家の塀に跳ね返り塀が汚くなる。それでも何週間もほったらかしにし、市の清掃局の人が掃除にくるまでほっておく。
もっとひどいのは、その家は自分の家から出るゴミを向かいの私の家の歩道に設置しているゴミ置きに平気で置いて行く、生ごみが置かれた時は大変である。
こんなであるから、会社での躾を指導するのは非常に大変である。「5S活動」を導入している企業が多いが、5Sの「清掃、整理、整頓、清潔、躾」のいずれにしても、ブラジルにはない習慣なので一つ一つ例を基に教えるのが大変である。
私が勤めていた会社では、毎月役員を中心とした5S巡回で職場ごとの5S実施診断を行っていたが、それ以上に部課長の毎朝の職場巡回の折に現場・現物で指摘・指導を繰り返して徐々に5Sを身をもって浸み込ませてきた。
一番大変なのは清掃である。掃除は清掃社員の仕事で、清掃はわたしの仕事ではないという考えを変えることである。後ほど「掃除までさせられた」と労働争議にならないために、職務規定に「自分の作業域は自分で、自分たちの職場は自分たちで清掃すること」と明記しておかなければならない。
極端な例で笑うに笑えない話であるが、1984年にマナウスに来て始めて従業員を採用し、仕事を始めた時、毎日、便器の上が靴の跡で汚れていた。話をよく聞いたら、便器の上に上がって用を済ましていることが分り、トイレの使え方まで絵にして教えなければならなかった。
反面ブラジル人の家の中に入ると驚くほどきちんと飾られ整理されている。まず日本人の家には物が多過ぎる。古いものでも、今使わない物でも「いつか使うかもしれない」と仕舞って置く物が非常に多く、タンスや引き出しの上、部屋の隅々に山積みにして置いてあり、部屋の壁が見えなくなっていることが多い。
また一般に装飾がへたであり、飾り物を玄間の靴箱や茶箪笥の上に無造作に置いてあるのが普通である。
反面、ブラジル人の家はどんな貧しい家を訪問してもシンプレスに無駄のない様にスッキリ、キチンと綺麗に整理されている。家庭に関しては、ブラジル人の方が清掃、整理、整頓できているのかもしれない。日本での四畳半で座っても寝ても手を伸ばせば何でも届く生活習慣などとても哀れで悲しくなるほどである。
2014年にブラジルで開催されたサッカー世界選手権(ワールドカップ)では、競技場で日本人サポーターが試合終了後、自分達の応援席のゴミを拾い、ゴミ袋に入れて綺麗に掃除し、競技場を後にする行動がブラジル国内で大きな話題となり幾度となくテレビで放映された。
それがきっかけで、日本での小学校で生徒達が自分達の教室やトイレを自分達で掃除する様子が同時に紹介され「これが日本の躾、美」と称賛された。
しかし、ブラジルでこんな事を生徒に強制したら「子供を奴隷、女中、掃除婦のようなことをさせて!」と父兄達から即反発を受け大きな問題となってしまうだろう。
「ピシャンソ」と言われる街の中の落書きもひどい。若者達が街中の塀、建物の壁すべてに、記号とも文字ともわからない落書きを塗装スプレーでする。よくもこんな高い、難しい所に書けるものだと驚く、とても難しい所にまで競え合って書かれている。
新しく塗装された壁、新しい建物、公共施設、記念塔などまでが被害にあっている。特にサンパウロ市はひどく「落書きアルテ」と呼ばれ、悪化をたどっている。マナウスから行くと街が非常に汚く見える。このような「ピシャドーレス」を取り締まる方法も法律もなく、十数年もの間放ったままになっている。
日本でも奇抜なトイレの落書きに「キミはいま、人類の未来を握っている」、「アノ部分には、人類の未来が秘められている」とか、「一歩前進」はあまり素っ気ないが「男ならじっと突き出せ筒先を、後へ引くとは卑怯千萬」などがある。