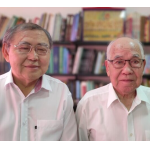みずほ文化協会(小野田貢会長)は25日(日)午前10時からみずほ浄心寺で先亡者追悼法要、11時から会館で「みずほ入植90周年式典」をサンパウロ州サンベルナルド・ド・カンポ市の同協会会館(Praça Tokuyama, 2, Cooperativa)で開催する。
小野田会長は「90周年記念事業として、会館の入り口に鳥居を作りました。二階建てバスも通れる大きなもので、高さ幅ともに6メートルあります。当日に通り初めをします。ぜひ皆さん見に来てください」と発表した。式典当日は、歴代会長、高齢者、功労者の顕彰、記念品贈呈などが行われる。当日は300人近くが訪れる予定で、太鼓部、カラオケ部、ダンス部がアトラクションを披露するという。
同地への日本人移民入植は1935年に10家族で60アルケールを買ったことから開始された。うち1アルケールを共有地として残したことから、そこに会館が建てられ、日本語学校が作られた。周りは工場ばかりになった今でも、コミュニティ活動が続く要因となったという。
編集部を訪れた同地在住のブラジル日系熟年クラブ連合会の上野美佐男元会長(90歳、山口県)は、「地主はイタリア人だった。地代の半分を前払いし、残りの金は2回分割払いで契約したが、期限よりも早めに払って完済した。当時は原生林みたいなところで、木を焼いて木炭を売って結構稼げたそうです。そのため『売るなら日本人』という信用が生まれ、以後、どんどん日本人が土地を買って入りやすくなり、一番最盛期の70年代には120家族ぐらい住んでいた時期もあった。日本語学校の生徒もその頃は120〜130人もいた」と懐かしがる。だがその日本語学校も現在はなくなってしまったという。
上野さんは「最初の人が信用を得てくれたから、あとが続いた。『一人の大金持ちも出ないが、一人の落伍者も出さない』と考えて組合を作り、売店を通して共同仕入れとかして、売上げの1%を資金として貯めた。そんな風にみんなで取り組んできた。70年代には養鶏村として名が売れたんです。グランジャ・伊藤も元は、みずほから始まったんです」という。
上野さんは「先に移住して成功していた同郷人の松本隆一さんが、1956年に一時帰国して『若者を5人ブラジルに連れて行きたい』と言った際、私が名乗り上げ、松本さんのいとこだった私の母も認めてくれたので、真っ直ぐにみずほに入った。以来、ずっとそこにいる」と述べた。
同地には20年誌、30年誌、40年誌、上野さんが編纂委員長をした60年誌まであり、それ以降は編纂されていないという。現在会長の小野田さん(88歳)も1955年に呼び寄せで同地に入植したので、今年入植70周年だという。
上野さんは「戦争中は安藤全八、菊地エイジ剣道五段とかも住んでおり、有名人も多数来た。中でも有名なのが1958年にきたノーベル賞受賞者の湯川秀樹博士。湯川博士の呼びかけに応じて、みずほ村が200コントの祖国支援をした。そのお礼に、移民50周年でブラジルに講演に来たおり、みずほに立ち寄って、入植5年目に建設された洗心堂で講演した。私も聞きに行きましたよ」と懐かしがった。