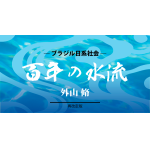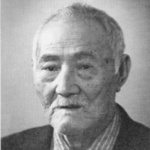ためにガソリン配給停止の要求は、米総領事自身が撤回した。
ためにガソリン配給停止の要求は、米総領事自身が撤回した。
以上の資産凍結令、ブラック・リスト、米総領事に対する戦いは痛快なほどの大反撃ぶりである。
戦時下の日系社会史上、輝かしい光を放っている。
なお、下元は役員をブラジル国籍者に代えるに際し、自身はフェラースの補佐役となったが「組合経営の実権は、このワシがしっかり握る」と周囲に確約していた。
が、一部の組合員は「フェラースは下元を食うぞ」と危惧していた。しかし逆に下元がフェラースを駆使しているのを見て、驚いたという。
下元は「もし連中が組合を食い物にしたら、この俺が日本刀で叩き斬る」とも断言していた。連中とは監査官と役員である。
しかし、下元は彼らと円満な関係を維持した。もっとも再々、意見を異にすることがあり、大きな声で論争するので、周囲はハラハラすることもあった。
が、それで怒って、反下元的な動きをする者はいなかった。彼らは下元を人間として観察するうちに、一個の傑物と評価するようになっていたのである。
いかにも下元らしい切れ味だが、実は、当人は極度の緊張が続いていた。この頃から、蘭の栽培を趣味にする様になっている。神経を和らげるためであった。
また一方で、下元は軍部に軽飛行機を二機寄贈している。コチアに対する風当たりが強くなるのを防ぐため、軍部を味方につけようとしたのである。
ただ、これは公表されなかった。されたら、ひと騒ぎ起きたであろう。
下元は以前、支那で戦う日本軍ため、組合員や職員に献金させたことがあった。
以前は日本軍、今度はブラジル軍では、いかにもマズイ。
運命の女神が微笑む
ところで、この戦時下、コチアにとって予想外のことが起こった。
常識的に考えれば、その事業は衰微した筈である。ところが、逆に興隆したのだ。それも飛躍的に…である。
例えば改選前は二、二〇〇人ほどであった組合員が、終戦の一九四五年までに一、〇〇〇人以上増えた。非日系人も多く加入した。
これは、次のような理由による。
戦争が長引き、様々な物資が不足、一般の農業者たちにとって、営農活動に差し支えるほど深刻化した。特にガソリン、貨物自動車、養鶏飼料などが手に入り難くなった。
が、コチアの場合はフェラースらブラジル人役員の人脈で、必要量を調達することができた。
それを知って日系、非日系を問わず、多くの農業者がコチアを頼ったのである。
結果的に、開戦時、傘下の事業所は七カ所だったが、その後一〇カ所、新設された。事業地域が広まったのだ。
組合員の生産物は、それまでのバタタ、トマテ、鶏卵、綿の他に落花生、薄荷、バナナ、茶などが加わった。
いずれも好価格で取引された。戦争特需の直接的・間接的影響で、市況が上昇したのである。
組合の事業総量は大きく伸びた。
こういうのを「運命の女神が微笑んだ」とでもいうのであろう。
そうした中、下元は一九四四年、出荷量の激増に対処、施設を拡充するという名目で、増資積立金(六章参照)を二㌫から五㌫へ引き上げた。
平時の感覚では暴挙であるが、この時は記録の上では大した波乱は起きていない。市況が良かったため、組合員は耐えられたのであろう。
戦中に増えた施設の価値は、戦前のそれの五倍に相当したという。
戦時下も新社会建設を追求
下元健吉は、六章で記した様に一九三〇代後半、日本から産青連運動を導入、新社会建設の狼煙(のろし)を上げた。
そして、以下、六章で記したことの繰り返しになるが、
「我々は、此処ブラジルで産業組合を組織した。組合運動の究極の目的は、新社会の建設である」
「産業、経済、教育、衛生、その他百般の事業を産組が統括、経営せよ」
と提唱した。
コチアだけでなく、日伯産業組合中央会に属する全組合の若者(組合員子弟や職員)に、その革命的構想を鼓吹し、奮起・結集させようとした。
これは奏功、一九四一年に「全伯産業組合青年連盟」が結成された。盟友五、〇〇〇名、日系社会史上最大の組織といわれた。委員長には下元が選出された。