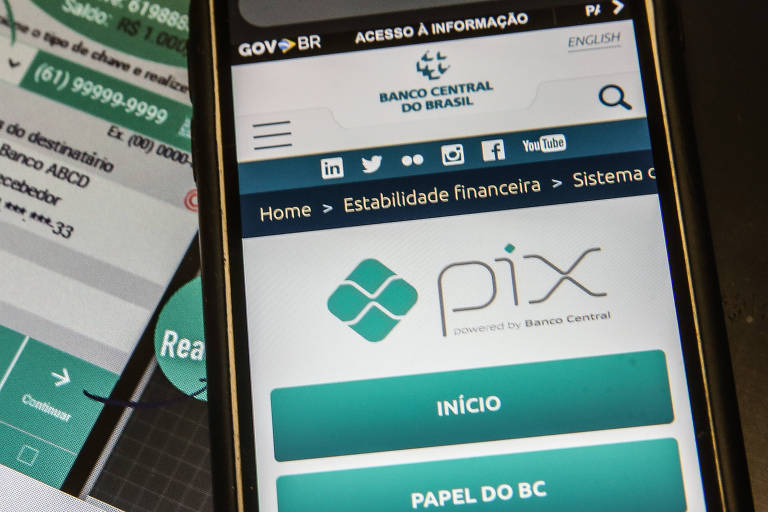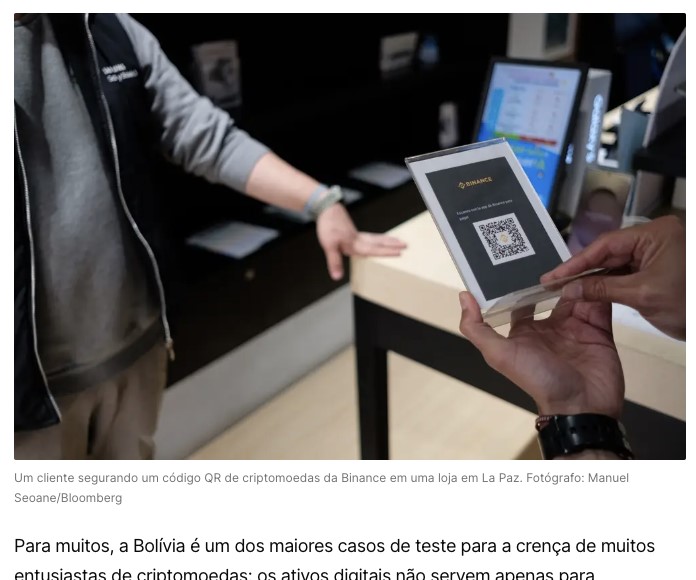COP30=ラゴ議長「変化は不可避」=参加国に決意伝える書簡

11月にパラー州ベレンで開かれる第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)議長のアンドレ・コレア・ド・ラゴ氏と事務局長のアナ・トニ氏が10日、全人類に共通する課題と懸念に対峙するため、国家間の団結の必要を強調する書簡を出したと同日付アジェンシア・ブラジル(1)が報じた。この各国担当者向けの書簡は、ブラジル側交渉責任者の意気込みと決意を伝えるもの。
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)に関する交渉担当者や関係者向けの書簡はブラジルのビジョンをまとめたもので、「私達の選択によるものであれ、大惨事によるものであれ、変化は不可避」「地球温暖化が制御されなければ、変化が押し付けられ、社会や経済、家族が混乱することになるだろう」といった言葉で、気候変動への対応が急務であることを強調している。
また、大惨事や冷笑主義、否認主義と闘うための回復力や行動のため、各国が正しい選択をする必要性も強調。提示されたアイデアは交渉担当者や中央政府だけでなく、他の関係者にも呼びかけるもので、196の国際条約締約国の枠を超えた諸国からの承認を得、「真の世界タスクフォース」を強化することを目指しているという。
ラゴ氏が例に挙げたのは、第二次世界大戦後に諸国が一体化し、国際連合が生まれたことだ。地球温暖化はデッドラインとされる産業革命前の平均気温を1・5度上回る状態に達しており、COP30という最後の機会を利用し、気候変動対策の時間を稼ぐ必要があるだろうとも強調した。
また、「11月にアマゾンに集まる際は、最先端の科学に注意深く耳を傾けると共に、森林と、森林を守り、森林に依存している人々が果たしている並外れた役割を再評価しなければならない」との言葉で伝統的な民の声に耳を傾ける必要性を強調した。
ラゴ氏は、パリ協定は機能しているが、交渉を行動に移し、効果的な結果に繋げなければならない。その役割は国家政策の立案者と政治指導者に課されており、拡大する気候危機に対して確固たる対応をとらなければ、将来的に尻拭いをする羽目になるだろうとし、「1世紀には気候変動での指導力を発揮しない世界的なリーダーは存在しないだろう」とも述べている。
ラゴ氏らにとり、COP30は地球規模の問題解決に向けた各国の取り組みを強化するためのてこの支点だ。「正当な交渉の場はパリ協定と気候変動条約で、交渉すべきことと他の組織に依存して実施することとの間には大きな隔たりがある」とも記した。
書簡では、パリ協定で規定した透明性メカニズムで、アラブ首長国連邦でのCOP28で初版が出た世界炭素収支(GST)にも焦点を当てている。各国はGSTに基づき、自国が決める貢献(NDG)と2年毎の透明性報告書の提出を進める必要がある。
最も脆弱な国の視点から緩和、適応、資金調達、技術、能力構築の問題に取り組む公正な移行作業プログラム(JTWP)に関する交渉はもう一つの懸念事項だ。また、アゼルバイジャンのバクーで開かれた前回会議で始まり、発展途上国の気候変動対策を保証するための資金調達の形態改善を軸とする、1・3兆米ドルに及ぶ取り組みの継続性も強調した。
COP30ではパリ協定離脱宣言後の米国の出方も注目されているが、ラゴ氏は米国企業の3分の2はパリ協定を尊重し、合意に従うと見ている。(2)
また、5日には、今回の会議は気候ガバナンスのための行動にとって決定的なものになるとし、発展途上国への資金援助とパリ協定の措置の加速が優先課題となるとの見解も表明している。(3)(4)