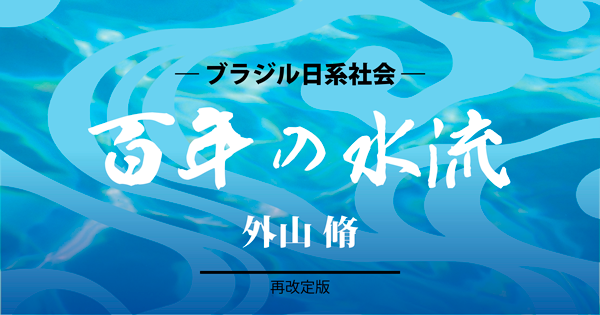日伯外交樹立130周年記念連載=第3回=食糧輸入国が世界の食糧生産基地に=セラード開発と日系人
かつて農作物を輸入で頼っていたブラジルが、世界の食糧庫と言われるようになって40年余り。ブラジルの食料自給率が急速に上がって輸出大国に変貌した要因の一つは、1979年に始まった国家事業セラード開発プロジェクトだ。そこに日本が技術と資金の協力を申し出て「日伯セラード開発協力事業(PRODECER)」を始めた結果、農地65%増、生産量は500%、生産性は300%増加し、現在では世界の穀物の40%を生産する世界有数の食糧供給国となった。
当時、緩やかに食糧自給率が下がり続け、食の安全保障に懸念が高まっていた日本政府の資金や技術の協力と、日本人移民や子弟のセラード開発が、ブラジルの食糧事情を大きく変える要因の一つとなった。
今回は、日本人移民や日系人が入植して、人参、葉野菜、ニンニクの国内生産の30%を支えているミナスジェライス州サンゴタルドを訪ねた。ここは「セラード開発のモデルケース」として有名だ。
熱帯サバンナ地帯と日本人を拒む地主
1973年、サンゴタルド市長に就任したジョゼ・ルイス・ボルゲス氏は、雇用も財源もない市の状況に危機を感じ、近郊にあるパトロシーニオで状況を相談したところ、セラード開発の提案と当時市場に大きな力を持っていたコチア産業組合中央会の井上ゼルバジオ会長を紹介されたという。ボルゲス市長がコチア産業組合に話を持ちかけると関心を示した。
当時、セラード地方の多くは私有地だった。そのため、ミナス州の中でも有数の資産家だった地主に話を持ちかけると、彼は驚くべき言葉を発したという。「ツバメのような日本人を受け入れたくない」と言い放ったのだ。
その言葉を受けたボルゲス市長は、当時の農林水産省アントニオ・デルフィン・ネット大臣をサンゴタルドに呼び、地主を説得させ、同年約60人以上の日本人と日系人が現地に入植しセラード開発を開始した。

気候が成功を導く
サンゴタルドに入植した多くの開拓者は、限られた土地で、米や大豆、コーヒーなど穀物の生産を始めた。しかし2月に寒波が来たことで、米はいもち病になってしまいうまくいかなった。
田中義文さん(84歳・鳥取県)に当時の話を聞くと、サンパウロ州イタチーバやボツカツを経て、独立してジャガイモの生産をしていたがうまくいかなかった。そこで1973年頃、コチア組合員のパトロンに相談したところ、サンゴタルドに一緒に行くことを提案され、家族で移住したという。
田中さんはサンゴタルドでもジャガイモ栽培を続けた。150ヘクタールにジャガイモの種を植えた後、45日間雨が降らず干ばつになってしまった。「ジャガイモは実らず大損をした」と話す。当時の田中さんのパトロンはこの痛い経験からサンゴタルドを撤退したが、標高1000mの涼しい気候に魅了された田中さんは残って農業を続けたという。
「研究者から、痩せた土地は改良することができるけど、気候は変えられない。サンゴタルドは気候に恵まれてると言われた」。この言葉を励みに田中さんは試行錯誤を続けた。
それまでの経験から、とうもろこしはうまく育つと思った田中さんは、早速50ヘクタールにとうもろこしを植えた。田中さんは「ここで初のとうもろこし生産者ですよ」と笑顔で話した。
今まで誰もとうもろこしを同地で生産していなかったため、当時のサンゴタルドのコチア組合にはとうもろこしの保存場所がなく、ミナス州政府の冷蔵庫を借りて収納していた。また、田中さんは流通ルートもわからなかったという。
たまたまジャガイモを運ぶトラックの荷物にとうもろこしもあることに気づいた田中さんは、その運転手を伝手に流通ルートを確保。現在、サンゴタルドではとうもろこしの生産も多い。人参やニンニクを植えた後、土壌改良のためになるという。

国内人参生産70%はサンゴタルド
標高1000mのサンゴタルドは温暖気候と適した土壌と適度な降水量、さらに灌漑技術を兼ね揃えており、1年中人参を育てることができる。様々な野菜や穀物を生産する中で日系人が発見した。
そのため、ほとんどの農家が人参を生産しており、ブラジル国内の70%の人参の生産を担っている。サンパウロ州をはじめ、リオデジャネイロ州、セアラ州、バイーア州等全国とウルグアイなど国外にも輸出している。
コチア産業組合が1994年に倒産した後に、農畜産業協同組合COOPADAP(Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba)が創立した。市の入り口に位置する同組合は現在、129農家に677人の職員が働いている。昨年、創設30周年を迎えた同組合はメモリアル館を施設内に建設し、今年2月に開館式を行なった。
メモリアル館には、開拓者のインタビュー動画や、農業生産時に使用していた器具の展示など今までの活躍ぶりが掲載されている。
COOPADAPでは後継者減を懸念しており、男性に限らない女性農家の育成に力を入れていて、育成プログラムを行なっている。また、近郊学校に出向き、農業の授業を子どもたちに向け行なっている。
[gallery link="file" columns="2" td_select_gallery_slide="slide" ids="446855,446853"]
サンゴタルドには組合に属していない大規模な農業企業も多くある。今年1月から同市市長になったマコト・セキタ氏は1500人を超える従業員を抱えた「Sekita Agronegócios」を経営している。また50以上のパートナー農家がいる。
セキタ家は、マコト氏の両親が日本からパラナ州に移住し農業を始めた。3人兄弟の長男タミオさんが1974年にコチア産業組合の一員としてサンゴタルドに入植した。マコト氏はその後1982年に両親と共にサンゴタルドへ移住した。
現在、9万(90mil)ヘクタールの土地を所有しており、主に人参、ニンニク、葉野菜、ベテハーバ、牛乳を生産している。同社は1年間に10万トンの食料を生産している。
約5千(5mil)頭の牛を飼育していて、うち約2千頭(2mil)が乳牛だ。ブラジル国内では4番目、ミナス州では1番目に多くミルクを生産しているとされていてブラジル国内の酪農産業をも支えている。
かつて、市内の住民に雇用機会さえなかったサンゴタルドは現在、北東伯から働きにくるなど多くの雇用を生み出している。日本人や日系人も開拓に加わったセラードでは様々な野菜が育ち、国内のみならず、国外にも輸出するほど大きな農業地帯と化とした。(島田莉奈記者、取材・動画撮影編集)