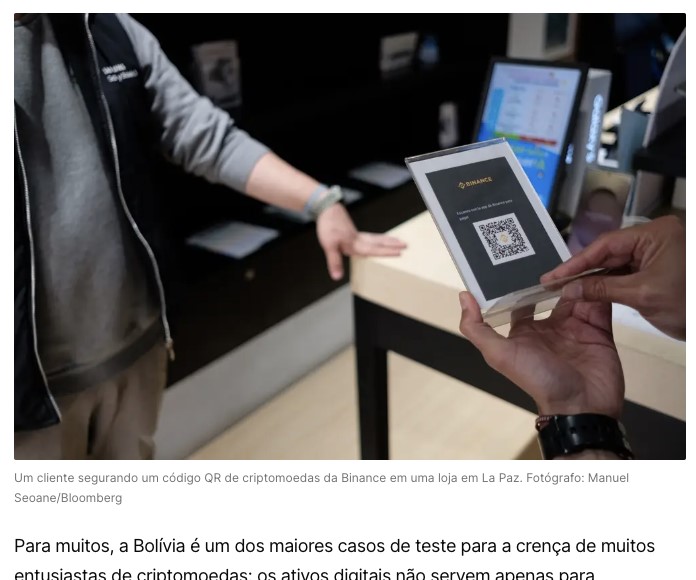〝高所得国〟チリの光と影=ブラジル発展への教訓とは?

『パンが二つある。あなたは両方食べる。私はどちらも食べない。平均消費量一人あたりパン一つ』(チリの詩人ニカノール・パラ)という言葉は、現在のチリの所得状況を象徴する言葉だ。というのも一人当たりの平均所得という数字は、大多数の現実を反映していないからだ。
「南米チリが高所得国に」――世界銀行の最新報告書が示すこの事実は、ラ米の中でも異例の経済成果として注目を集めている。自由貿易の拡大や国外からの技術移転を軸にした政策が功を奏し、チリは1980年代以降、安定した経済成長を実現してきた。
だがその経済指標の裏側には、年金の低さや非正規雇用の増加、根強い所得格差が国民生活を圧迫している現実がある。チリの事例は、経済成長と社会的包摂の両立という、途上国共通の課題を浮き彫りにしている。このチリの経験が、ブラジルにとっていかなる教訓となり得るかについて、26日付エスタード紙(1)が報じた。
同報告書によれば、チリの1人あたり国内総生産(GDP)は1万5800ドルで、ブラジルの9280ドルを大きく上回り、高所得国の基準である1万3845ドルも超えている。背景には1986年以降に本格化した経済改革があり、成長の黄金期はエイルウィン政権(1990〜94年)からバチェレ政権(2006〜10年)までの中道左派「コンセルタシオン」政権期に集中していた。この間、自由貿易協定の拡充や海外との連携など開放政策が進められた。
エイルウィン政権期には年平均7・3%、続くフレイ政権(1994年~2000年)でも5・7%の成長率を記録。2000年代以降も景気後退を伴いながらも成長は持続した。元中銀副総裁ホアキン・ビアル氏は「一貫した経済政策が成長を支えた」が、「現実には今も所得分配の不平等が深刻」と警鐘を鳴らす。
チリの経済基盤は、ピノチェト軍政時代(1973〜90年)に導入された「新自由主義」的改革に起源を持つ。価格自由化や規制緩和、国営企業の民営化など、市場原理に基づいた政策が導入され、経済の開放性が高まった。米国で経済を学んだチリ人経済学者グループ、通称「シカゴ・ボーイズ」が中心となって策定した改革案「エル・ラドリージョ」には、その後の政策の骨子がまとめられていた。
だが1982〜83年には金融・企業危機が発生し、失業と貧困が急増した。現在も格差は解消されておらず、ジニ係数(所得の不平等さを測る指標で、0に近いほど平等、1に近いほど格差が大きい)は2000年の0・53から2022年に0・43まで改善したが、体感との乖離は大きい。
首都サンティアゴ在住のアナ・マリア・カンピージョさん(72歳)は「統計は多数派の現実を映していない」と語り、月15万ペソ(約2万2千円)の年金と20万ペソ(約3万円)の補助金で暮らす生活の厳しさを訴える。移民増加以降は非正規雇用も増え、高齢者の中には月5万ペソで暮らす人もいるという。
チリ大学の経済学者ロベルト・アルバレス氏は、ブラジル経済には国際市場との統合という大きな可能性がある一方で、高関税や構造的な汚職が成長の妨げになっていると指摘。ビアル氏も「チリより規模が大きく複雑な国に単純な提言はできない」としつつ、「経済自由化の推進、財政の安定が持続的成長に不可欠だ」と強調し、このチリの経験はブラジルが今後の方向性を考える上で重要な手がかりとなり得るとした。