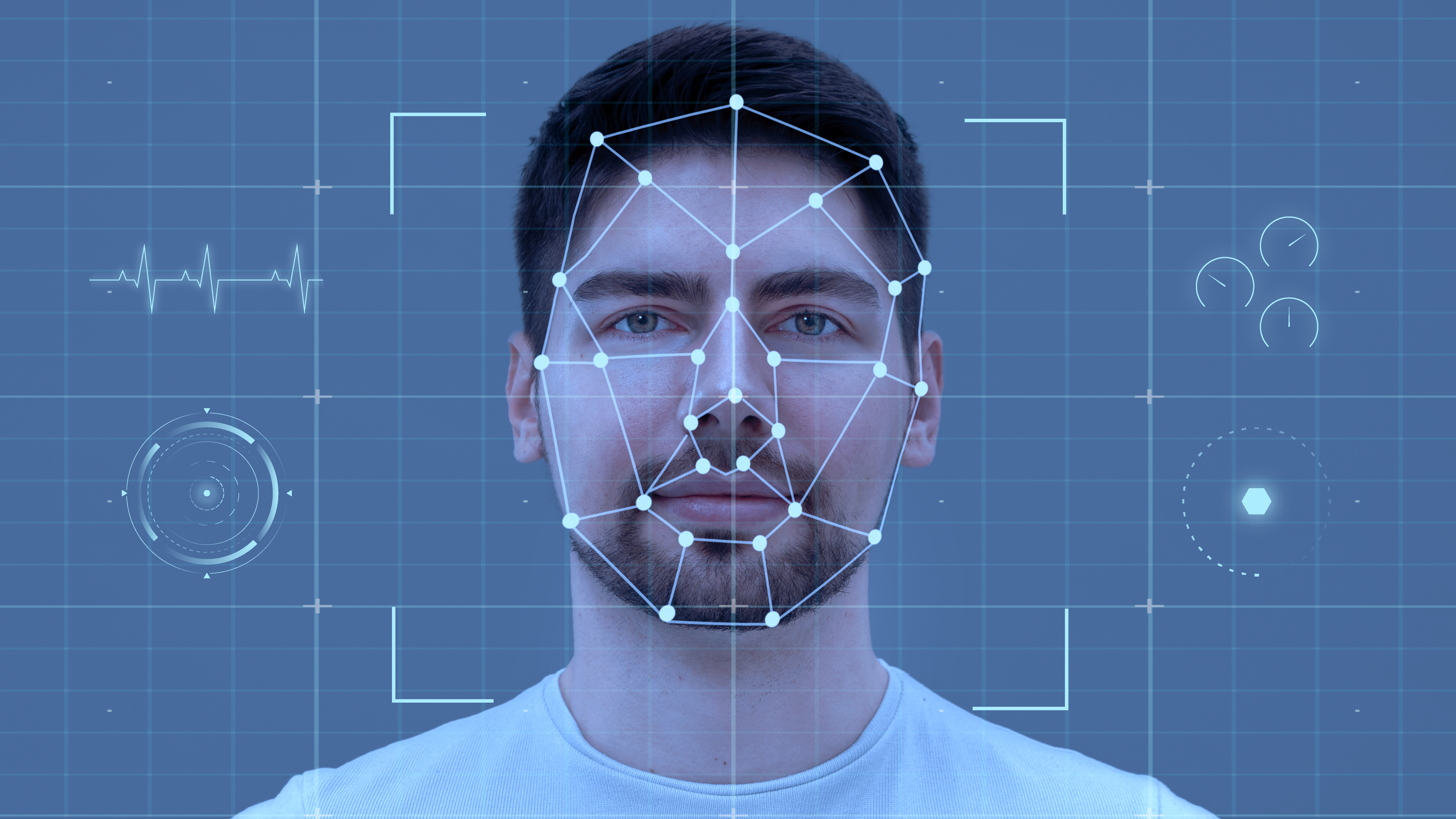Selic=1PP引き上げで14・25%に=年内に15%まで上昇に現実味

中銀通貨政策委員会(Copom)は19日、経済基本金利(Selic)を年率13・25%から1%ポイント(PP)引き上げ、14・25%とすることを全会一致で決定した。金利引き上げは5会合連続で、これにより、ジルマ・ロウセフ大統領(当時)の弾劾を引き起こした、2015年7月末〜16年10月の経済・政治危機時と同等の水準に達した。中銀は5月6〜7日の次回会合で更なる金利の引き上げを示唆しており、年末には15%に達する可能性もあるという。20日付G1など(1)(2)(3)が報じた。
中銀の経済動向予測調査「フォーカス」によると、広範囲消費者物価指数(IPCA)で見た25年のインフレ率は5・66%に達し、目標中央値の3%のみならず、上限の4・5%さえも遥かに上回ると予想されている。
インフレ圧力の要因としては、「行政管理価格」と「サービスインフレ」が特に注目されている。
行政管理価格は政府または市場によって管理される価格で、電力、食品、水道料金、燃料、公共交通運賃などがこれに該当する。価格は供給と需要の法則に従わず、政府や市場によって設定される。2月には月初に実施された商品流通サービス税(ICMS)引き上げが影響し、燃料価格が2・89%上昇し、12カ月累計のIPCAは5・19%に達した。これらの価格はドルの価値や国際的な石油価格、気象条件などによって決まるため、Selicでは調整できない。
一方、サービスインフレは供給と需要の影響が大きく、過剰な需要が価格上昇を招く。サービスはIPCAの約35%を占め、家賃、教育費、医療保険、交通、レジャー、外食など、家計にも大きな影響を与える。また、サービス価格の上昇は心理的なインフレを引き起こし、消費者が価格上昇前に商品を買い込む傾向を強めるため、結果的にインフレをさらに悪化させる。
サービスインフレは2月までの12カ月累計で5・32%に達しており、季節調整後は8%に達するという予測もある。背景には、労働市場の過熱、インフレの遅延反映、エネルギーや原材料のコスト増がある。
国内の失業率はかつてないほど低く、消費が増している一方、人手不足で企業は賃金を引き上げざるを得なくなっており、サービス価格の上昇を招いている。Selic引き上げは消費熱を冷ますために重要で、金利上昇により貸出金利が上昇し、不動産や自動車などの大型商品の購入が抑制されれば、サービスの需要も徐々に減少する。金利引き上げの効果は通常、6カ月程度後に現れるため、現在の金利水準が維持されることで、消費抑制とインフレ抑制が期待される。
インテル銀行は、Selicは0・50PP引き上げられて14・75%に達したが、11月には引き下げが始まると予測。一方、XP証券は0・75PPと0・50PPの2回の引き上げで年15・50%に達すると予想。引き下げ開始は来年初めからと見込んでいる。
XPの経済学者ロドルフォ・マルガト氏は、金利引き上げの必要性を「サービス部門でのインフレ圧力と旺盛な需要に対処するため」と述べ、26年には金利が12・50%に低下する予測を示した。だが、これには経済の適切な減速と財政管理が求められると付け加えた。
高金利による経済の減速リスクが懸念される中、エコノミストたちはブラジルが景気後退(リセッション)に陥ることはないと予想。フォーカスでも25年の国内総生産(GDP)の成長率は1・99%と見ている。マルガト氏は、「インフレ慣性を抑えるため、金利引き下げは、インフレが中期的に目標中央値の3%に収束する明確な兆候が現れるまで始まらない」と指摘した。